| ■チャーガの歴史 一口メモ |
|
|
|
《古代》
5,000年前の古代人のミイラの腰布からなんとチャーガが発見されました。こんなに古くからチャーガが健康維持に使用されていたことになります。
1991年、オーストラリアとイタリアの国境近のイタリア領南チロル自治州のハウスラフヨッポ付近、標高3210メートルの地点で、氷の中から凍結した新石器時代のミイラが完全な形で発見された。
紀元前3300年頃の男性で、携帯品や服の断片からも興味深い事実が明らかになった。
高山の氷河の中で、5,000年もの間、腐敗せずに、生前そのままの状態で凍結保存されていたのは、前例がなく、考古学や古代の生活を研究する学者達の恰好の研究対象となった。
このミイラの男の携帯品から白樺のキノコ(チャーガ)が発見されたことから、彼は5,000年前に、すでに旅に一種の健康食品を携行していた訳であり、チャーガは、新石器時代から、病気の治療目的として、人々に飲まれていたと推定されています。
いわゆる民間で伝えられた方法は、すでに先史時代にその起源を持っているものであり、以来何世代にもわたってそのやりかたが伝えられてきたのである。
|
|

5,000年前の古代の男の人発見についての本
|
|
|
《紀元1世紀》
ギリシアの医者、ディオスコリデスがすでににこのキノコ・チャーガについて説いている。
このキノコが体に有用であると説いており、まず乾かし、細かくひいて、熱湯を注ぐ。
こうして何世紀もの間飲まれてきたと言う。
また聖書の外典には、シラカバのキノコ・チャーガに幻覚的な効果があると記されているが、
これは証明されていない。
|
|
|
|
|
《中世》
11世紀の聖ヒルデガルト・フォン・ビンゲンは、樹木のキノコを6種挙げており、その中でシラカバのキノコ・チャーガにも言及している。
古代ロシア年代記には、ヴラジミール・モノマプ(キエフ大公1053-1125)が、唇にできた腫瘍をチャーガで治した、と記されています。
16世紀のロシア帝国皇帝ロマノフもチャーガを飲んで口唇ガンを直したらしい。
アイヌの人たちはチャーガをお茶代わりにして飲んでいたらしい。かなりの貴重品扱いをされた。
|
|
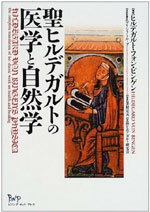 聖ヒルデガルト・フォン・ビンゲンについての本 聖ヒルデガルト・フォン・ビンゲンについての本
|
|
|
|
|
《近代》
チャーガはロシアの医師が研究し、それを世界中に広めたのは、ソルジェニーツイン。
チャーガを世界中に広めたのは、ロシアのノーベル賞作家、ソルジェニーツイン(1918〜2008年)である。
ソルジェニーツインが1953年末、南カザフスタンへの流刑生活中にガン(悪性腫瘍)を患い、死線を彷徨うが、マースレニコフという医師と出会い、彼の勧めでチャーガを服用して自分のガンが治癒したことに感動し、小説『ガン病棟』(1968〜1969年)を執筆したことで、チャーガは世界中に広まった。
ソルジェニーツインは、よほど感動したのでしょうね、唯一、治療に当たってくれた、自分の命の恩人の医師だけを、なんと小説中に実名で登場させたのである。
それが、マースレニコフという医師だ。
彼こそ、ソルジェニーツインのガンをチャーガで治してくれた実在の医師なのです。
それにしても、この小説、『ガン病棟』によって、チャーガでガンが治る、ということを世界中の人に知らしめたのです。
チャーガ、そう、カバノアナタケのことです。
マースレニコフは徹底的にチャーガを研究して、しまいにはロシア科学アカデミーでチャーガを正式に医薬品として認可させることに貢献した、いわばチャーガの最大の功労者とされる。
|
|

ソルジェニーツイン氏
(1918〜2008年) |
《医師・マースレニコフ(1884〜1966年)》
『ガン病棟』に登場する、このロシアに実在する医師、マースレニコフは1884年生まれ。
1908年にモスクワ大学医学部卒業後、アレクサンドルの病院(当時は田舎の小さな病院だった)に赴任。
狩猟好きなマースレニコフは、ある時、狩猟の途中で立ち寄った小屋で、森番からチャーガのお茶をごちそうになりながらの雑談の中で、このお茶は当地で昔から体に良いと伝えられていることを聞き、とても興味を持つようになったのです。
またある時、マースレニコフ医師はもう1つの事実に気が付いた。彼の勤務する病院に来る農民患者には癌が滅多に見られない。また病人も少ないというのはどういうわけだろう!!!
ここで、もしかしたら、このチャーガか? 」と、マースレニコフの頭の中で、その二つが結び付く。この気付きをきっかけに、これを実証する為の調査を始め、彼の長い研究にのめりこんでいく歴史が始まるのである。そして、先ずその謎の糸口・一つの確信を突き止めた。
やはり、この辺り一帯の百姓たちはお茶代を節約するために、茶ではなくて『チャーガ』を煎じて飲んでいるという事実を!
それは『白樺の茸』とも言われている『白樺の癌』。古い白樺の木によくある妙な格好の瘤のような物。
表面が黒く、内側が暗褐色をしている自生のチャーガのことなのです。
彼の憶測ではロシアの百姓は、自分たちが気付かないうちに『チャーガ』でもって何世紀もの間、癌から救われていたということです。
しかし、推測するだけでは勿論、足りません。彼はもっともっと詳しく調べなければならないことを自覚し、先ず自分自身がチャ−ガを飲んでみて副作用がないことを確かめた上で、徐々に患者に投与していくことにしました。
自家製煎じチャーガ茶を飲んでいる者と飲んでいない者とを何年も続けて観察し、腫瘍患者にそれを飲ませてみては観察しました。
これはほかの治療法を中断することになるから、ちょっとやそっとでできることじゃない。それに何度のお湯で煎じるのか、分量はどれくらい使うか、沸騰させるのかどうか、コップで何杯飲んだらいいのか、副作用はないか、どんな腫瘍に効き、どんな腫瘍にはあまり効かないか、などと問題はたくさんある。それを博士は一つ一つ研究していった……
すると、驚くことにチャーガが癌転移を抑え、食欲を増進させるという事実が判明した。
---この文章の多くは、ソルジェニーツィンの著書「ガン病棟」からの抜粋です---
そして、さまざまなチャーガの有用性を明らかにし、それらをまとめた論文を学術誌に載せるとその反響は大きく、1920年から1930年代にかけて、ソ連にチャーガブームが巻き起こったという。
そして、各地から飲用相談の手紙が寄せられ、また、チャーガを自分でも処方してみたいという医師の相談にもマースレニコフ医師は丁寧に応じ、チャーガは少しずつ目立つ存在になっていった。
|
|
 マースレニコフ医師(1884〜1966年)、額はソルジェニーツィン マースレニコフ医師(1884〜1966年)、額はソルジェニーツィン |
|
|

「ガン病棟」(1968〜1969年) |
《チャーガと出会ったソルジェニーツイン》
そういうブームのなかで、ソルジェニーツィンもマースレニコフ医師に自身のガンについての相談の手紙を出したのである。
チャーガがあまりにも大きな存在になり、しかもそれがいつまでも続いたことから一時ソ連行政機関からの圧力がかかってマースレニコフは活動が圧迫されたりもした。それにも負けず彼は1956年にチャーガについての特許を取得。ようやくソビエト保険省からチャーガがガン毒性低下剤として承認されたのです。
また、モスクワ市に70床のクリニックを提供され、マースレニコフ博士はそこを拠点に研究活動を続け、1966年に82歳で他界するまで『チャーガ』の研究に努めた。
残念ながら、マースレニコフ博士の書籍は日本にはあまり見当たらない。
マースレニコフ記念館には、マースレニコフ博士の指導でチャーガの研究を行った人々の膨大なカルテも保存されており、手紙で飲用指導を受けた人々からの報告文書もあった。そのなかには、チャーガをよく飲んだソルジェニーツィンが、マースレニコフ博士に送った直筆の礼状もあったのである。
ソルジェニツィン自身の説明によれば、この作品は正確な時と所のデータをそなえたポリフォニック(多位性)な、主人公のいない長篇であり、「所」はウズベク共和国の首都タシケント市の総合病院のガン病棟(ソルジェニツィン自身が流刑生活中にこの病院で腫瘍を治療してもらった)。
|
|
《ガン病棟 第一部》 【白樺の癌】
ガン治療薬としてのチャーガを世界中に広めることになった ソルジェニーツインの著、『ガン病棟』 (1968〜1969年執筆)。
それは、 ソルジェニーツインが政治犯として南カザフスタンへの流刑生活中に、1953年末、ガン(悪性腫瘍)を患い、死線を彷徨うが、ガン治療で有名なマースレニコフという医師の話を聞き、手紙を出して助けを求めた。そしてタシケント市の総合病院で彼によってチャーガを服用してもらい、ガンが治癒したことに感動し、この小説を執筆した。この中には、マースレニコフ医師の研究や、チャーガの飲み方などがとても詳しく記述されている。或いはソルジェニーツインは、自分の命の恩人であるチャーガとマースレニコフ医師を詳しく描写することで、ガンに苦しむ多くの人々へ贈る、いわば《ガン克服マニュアル》或いは《チャーガの飲み方の処方箋》という意味合いも持たせているのではないか、と思われる。 そして、この小説を発表することによって、チャーガでガンが治る、ということを本当に世界中の人に知らしめたのです。
名著として名高いのですが、現在は絶版になっています。
以下は、その一部の抜粋。
「最初から順序立てて言うと、こうなんだ、シャラフ。
マースレニコフ博士のことは、さっき言った外来患者が教えてくれた。つまり博士はモスクワ郊外のアレクサンドロフ郡の田舎医者で、もう何十年も同じ病院に勤めている。以前はそういうことが認められていたらしいね。
で、博士は一つの事実に気がついた。
私はここにいる!忘れてはいけない!)
「……博士は調査を始めた。調査を始めた」コストグロートフは同じ言葉を繰返した。ふだんは決してそんな癖はないのだが、今は繰返すことが楽しそうだった。「そして、こういうことを発見した。
すなわち、そのあたり一帯の百姓たちは、お茶代を節約するために、茶ではなくてチャーガというものを煎じて飲んでいる。それは白樺の茸とも言われて……」
「ヤマイグチ(マツタケ目アミタケ科、白樺林に発生する食用茸)のことか」と、ポドゥエフが口を挟んだ。ここ数日、絶望感にひたりきっていたエフレムにも、これほどありふれた、これほど手に入りやすいものはたいそう魅力的だった。
ここの患者たちは南国人が多かったので、ヤマイグチはむろんのこと、白樺そのものさえ一度も見たことがなく、したがってコストグロートフの言っているものを思い浮かべることはむずかしかったようである。
「いや、ヤマイグチじゃないんだ、エフレム。正確に言うと、これは白樺の茸じゃなくて、白樺の癌なんだ。ほら、古い白樺の木によくあるだろう……妙な格好の瘤のような、表面が黒くて、内側は暗褐色の……」
「サルノコシカケか」エフレムが言った。「昔は火口がわりに使ったっけ」
「そう、たぶんそれだろう。マースレニコフ先生はふと気がついた。ロシアの百姓は自分たちはそれと気づかずに、そのチャーガでもって何世紀ものあいだ救われていたのではなかろうか、とね」
「使用法を、それじゃ読み上げるから、みんな書きとってくれないか」と、コストグロートフは大声で言った。一同はざわめき、お互いに鉛筆や紙切れを融通し合った。パーヴェル・ニコラーエヴィチは何も持っていなかったので、(自宅に帰れば、ペン先が軸の中に隠れる新式の万年筆があるのだが!)ジョームカが鉛筆を貸してやった。
シブガートフも、フェデラウも、エフレムも、筆記の準備をした。準備ができたので、コストグロートフはゆっくりと手紙の文面を読みあげ始めた。
生乾きのチャーガをどうやって擂りおろすか、何度ぐらいのお湯で煎じるか、どうやって濾すか、何杯ぐらい飲むか、等々………
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|